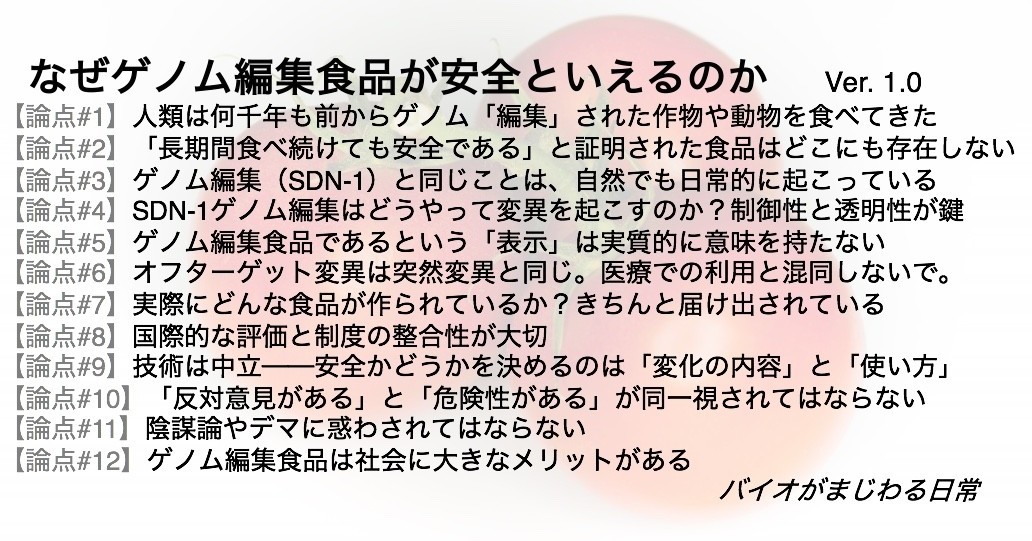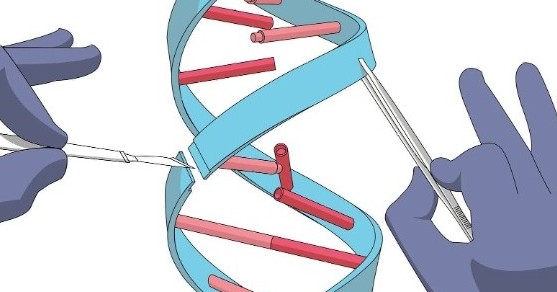「遺伝子組換えでない」「国産」という表示の裏側──GMO大豆の国際政治と消費者心理✉️33✉️
アメリカの中西部の大豆の収穫期。広い穀倉地帯では、サイロ(穀物を保管する施設)がすでにいっぱいになりつつあります。しかし、問題があります。肝心の「買い手」がいないのです。世界最大の大豆輸入国である中国が、新しいシーズンのアメリカ産大豆を一件も契約していないからです。
これは単なる貿易の停滞ではありません。米中の関税交渉の中で、アメリカの「遺伝子組換え(GMO)大豆」が交渉の“切り札”として使われているのです。
この影響は日本にも及んでおり、日米間の関税交渉や、トランプ大統領の来日に関する報道でも取り上げられています。

中国がアメリカの農家を追い詰める理由
中国は最近、ブラジルやアルゼンチンといった南米産の大豆にシフトしています。これは単なる貿易の争いではなく、国家の安全保障や食料の自給、さらにはバイオテクノロジーをめぐる戦略的な動きでもあります。つまり、中国はアメリカに圧力をかけるために、大豆という「食料」を武器にしているのです。
アメリカ農務省(USDA)の最新データによると、2024年にはアメリカで栽培される大豆のうち、96%が遺伝子組換え品種になりました。1997年にはわずか17%だったので、約25年で6倍近くに増えたことになります。もはやアメリカの大豆のほとんどが、合成生物学の技術によってつくられた「GMO大豆」なのです。
これらの大豆は、除草剤であるグリホサートなどに強いように設計されており、農家は雑草管理のコストを下げ、安定した収穫を得られるというメリットを享受してきました。しかし、中国が輸入を止めてしまった今、その利点が裏目に出ています。大豆の値段は下がり、肥料や農薬のコストは上がり、倉庫には売れない大豆が山積みになっています。
大豆が外交カードになっている
トランプ政権時代、アメリカ政府は「関税収入で農家を支援する」と約束しましたが、実際には支援の手続きが遅れ、多くの農家が不満を募らせています。いまやアメリカ中西部の農村は、ワシントンと北京の政治的駆け引きの犠牲になっているのです。
中国が大豆を「買わない」と決めたのは、単なる報復ではありません。アメリカ政府に圧力をかけるための戦略です。大豆農家は共和党支持者が多いため、ここを揺さぶればトランプ政権に打撃を与えられるというわけです。ただし、中国も大豆をまったく買わないわけにはいきません。国内の需要が大きいため、交渉のタイミングを見計らって「大規模購入」を発表することがあります。こうした政治的な駆け引きが、国際市場を揺さぶっているのです。
日本も無関係ではない
この米中対立の影響を最も強く受けているのが日本です。日本は大豆の多くをアメリカから輸入しています。食用の国産大豆もありますが、アメリカから輸入する大豆の大部分は家畜のエサや食用油、加工食品の原料として使われます。
しかし、ここで注目するべきは、アメリカから輸入される大豆のほとんどがGMOであることです。一方、日本では「遺伝子組み換えでない」という表示が重視され、消費者もそうした商品を選ぶ傾向があります。そのため、輸入が増えても、人が直接食べる食品にはあまり使われず、見えにくい形で間接的に消費されているのです。
「非GMO」と「GMO」の二重構造
日本の大豆市場は、実は「二重構造」になっています。スーパーに並ぶ「国産大豆」や「遺伝子組み換えでない」と表示された商品は、国産の非GMO大豆、あるいはブラジルなどからの非GMO大豆を使って作られています。一方で、価格の安いGMO大豆は飼料や油として使われています。
非GMO大豆は分別管理が必要なためコストが高くなります。そのため、価格の差が広がり、「安全・安心」を重視する層と「価格重視」の層の間で消費の格差が生まれています。
さらに、環境問題も無視できません。GMO大豆の普及によって農薬の使用量が減った地域もありますが、一方で「耐性雑草」が広がるなどの副作用も報告されています。除草剤グリホサートをめぐる健康リスクの議論は、科学的な論争を超えて、政治や感情の問題にもなっています。
大豆と地政学の関係
大豆は単なる農作物ではなく、世界のタンパク質供給を支える重要な作物です。同時に、外交や経済戦略の道具でもあります。米中関係が悪化するたびに、大豆の価格は乱高下し、日本の食料価格や畜産業にも影響を与えます。
アメリカはGMO技術によって効率的な農業を実現しましたが、中国は輸入依存からの脱却を目指して、南米への投資や自国のバイオ産業を強化しています。日本はその狭間で、「誰から、どんな大豆を、何のために買うのか」という問いに直面しています。
これからの日本の戦略
短期的には、アメリカとの関係を保つために輸入を増やすことが現実的でしょう。しかし、「遺伝子組み換えでない」表示を重視する消費者心理が変わらない限り、長期的には、国内の大豆生産を強化し、非GMO原料を安定的に確保する必要もあります。たとえば、国産大豆を使った食品の拡大や、バイオ燃料や新素材への応用など、「食べる大豆」から「使う大豆」への転換も求められています。
結びに
アメリカの倉庫に積まれた大量のGMO大豆。中国の港に届かないままの穀物。日本が輸入するGMO大豆と日本のスーパーマーケットにならぶ非GMO大豆食品。その背景には、世界の政治と経済、そして食卓が複雑に結びついた現実があります。
GMO大豆の話題は、単なる農業の話ではありません。それは、合成生物学という新しい技術と、国際政治・食料安全保障、そして日常生活で利用するスーパーマーケットの大豆製品がまじわる21世紀の物語なのです。
すでに登録済みの方は こちら