合成生物学はジャズーー遺伝子操作された生物を野外に放してよいのか?✉️30✉️
「人間は、遺伝子を操作した生物を、自然界に放ってよいのか?」
「人間は、遺伝子を操作した生物を、自然界に放ってよいのか?」
この問いは、単なる技術論でも、倫理論でもありません。むしろそれは、「人間と自然の関係をどう考えるか」という文明的な問いの形をとって、21世紀の科学の核心的なトピックになっています。
バイオがまじわる日常✉️28✉️でも紹介した話題です。しかし、日本国内では議論するメディアがほとんどありません。
このことを考えるうえで、10月20日の米公共ラジオ放送NPRの番組の内容が、興味深いものでしたので、今回はこの内容を中心に紹介したいと思います。
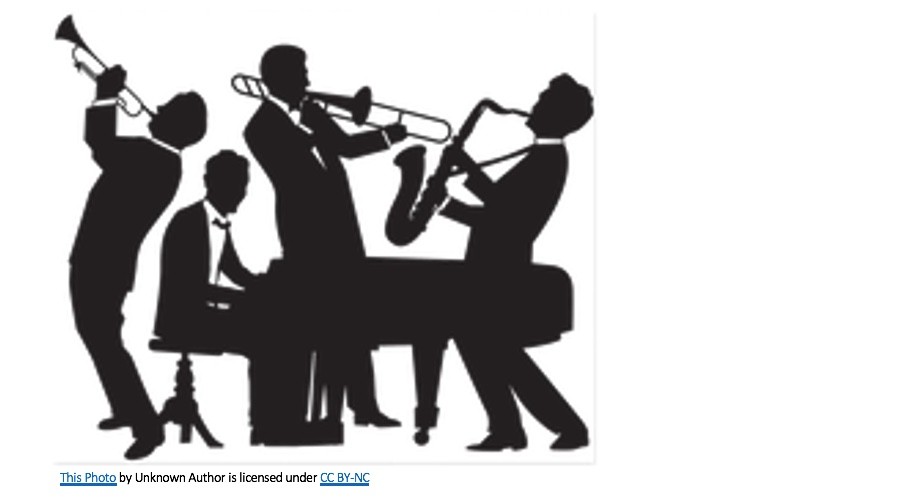
カエルを救うために、遺伝子を改変する?
発端は、オーストラリアのマッコーリー大学で両生類を研究するアンソニー・ワドル(Anthony Waddle)の試みです。
彼が注目したのは、世界中のカエルを絶滅寸前に追いやっている「カエルツボカビ症(chytrid fungus)」という感染症でした。この菌は、両生類の皮膚に感染し、呼吸や水分の調整を妨げる致命的な病原体です。すでに南極を除くすべての大陸に広がり、科学者たちはこれを「史上最悪の生物多様性の危機」と呼んでいます。
ワドルは、カエルの体がもともと抗生物質のような物質を出して自らを守っていることに注目しました。しかしツボカビは、その防御をも突破してしまう。「この病気を根絶するには、環境を浄化するよりも、カエル自身を変えるしかない」――。彼はそう考えました。
彼が取り組んでいるのは、カエルのゲノムにツボカビ耐性遺伝子を導入するという実験です。
遺伝子工学の力で、病気に強いカエルをつくり、自然界に戻す。一見、絶滅を防ぐ夢のような方法に思えますが、ここにこそ「人間はどこまで自然を再設計してよいのか」という大きな問題が潜んでいます。
「合成生物学」は、ジャズのようなもの?
この新しい領域を、科学者たちは「合成生物学(synthetic biology)」と呼びます。
定義は曖昧です。ある研究者はこう言いました。「合成生物学はジャズのようなもの。定義しづらいけれど、見れば分かる。」
つまり、ひとつの厳密な技術というより、生命を設計し、改変するための多様なアプローチの総称なのです。ゲノム編集、人工細胞、DNA合成、生体回路設計――。どれも「生命をエンジニアリングする」という思想のもとに展開されています。
たとえば、私たちはすでにこの技術の恩恵を日常的に受けています。合成インスリンやワクチン、病害に強い作物、発酵バイオ燃料など、これらはすべて合成生物学の成果です。
しかし、これまではその実験場が「ラボ(実験室)」の中に限られていました。問題は、その境界がいま、ゆっくりと自然界へと広がろうとしていることです。
実験室の外に出たら、もう戻せない
合成生物学が自然界に及ぶとき、もっとも懸念されるのは「不可逆性」です。
研究者はこう語ります。「もし改変した生物を野外に放ち、それが予期せぬ影響を及ぼしたら、元に戻すことは不可能だ。」
ウイルスや細菌のように、遺伝子改変された個体が繁殖し、世代を超えて変化を伝えることもありえます。しかもその変化が、他の種や生態系全体に波及する可能性もある。「野外に放ったハエの遺伝子を回収することができるか?」という問いに、誰も明確な答えを出せません。
自然の複雑さを前に、人間の「制御できる」という思い込みがどこまで通用するのか。この問いは、科学よりも哲学に近い響きをもっています。「私たちは本当に、自然を再設計し続けるほど賢い存在なのか?」
IUCNの会議――世界が下した「微妙な判断」
この議論は、いまや学界だけのものではありません。2025年10月、アブダビで開かれた国際自然保護連合(IUCN)の世界会議で、合成生物学をめぐる方針が正式に審議されました。
IUCNは世界の保全政策に大きな影響を持つ組織で、各国政府とNGOの両方が加盟しています。絶滅のおそれのある野生生物のレッドリストでよく知られています。
今回の会議では、合成生物学に関する2つの提案が投票にかけられました。
1つ目は、遺伝子改変された生物の野外放出を一時的に禁止する「モラトリアム」。
2つ目は、すでに研究が進行している現状を踏まえ、安全性評価と倫理基準を整備する「指針」を採択する案です。
結果はきわどいものでした。モラトリアム案はわずかな差で否決され、指針案が採択されました。つまりIUCNは、「全面的な禁止」ではなく、「慎重に管理された利用」を認める方向に舵を切ったのです。
「ブレーキをかけるか」「アクセルを踏むか」
モラトリアムを支持したのは、ヨーロッパの生物学者 Ricarda Steinbrecherらです。彼女は「自然はすでに極めて脆弱な状態にある。新技術の導入には慎重であるべきだ」と訴えます。
「ウサギをオーストラリアに導入したとき、誰がそれが生態系を破壊するほど繁殖すると思ったでしょうか。」彼女は、過去に善意の介入が生態系を壊した例をいくつも挙げます。
技術への過剰な信頼が、取り返しのつかない事態を招くかもしれないというのです。
一方、反対にモラトリアムに反対した科学者たちは、まったく違う危機感を抱いています。Revive & Restoreの共同創設者Ryan Phelanは言います。
「私たちは、もう時間がないのです。」
地球の気温上昇と森林破壊のスピードは、かつてない速さで進行しています。サンゴ礁では、すでに数百種のサンゴが消えつつあり、その多くは記録すら残っていません。
「自然の回復をただ待つだけでは、失われていく方が早い。人間が積極的に介入しなければ、保全そのものが成立しない」――。彼らの主張は、倫理よりも“緊急性”に基づいています。
「チワワもオオカミも同じ種」という反論
ワドルは、慎重派の主張を理解しつつも、こう言い返します。「チワワもオオカミも同じイヌという種です。人類はすでに、自然を根本的に変えてしまった。」
彼にとって、遺伝子改変は禁じられた行為ではなく、人間がすでに行ってきたことの延長です。むしろ問題は、技術をどう使うか、どのような目的に使うかにある。「これまで自然を搾取するために技術を使ってきたが、今度は守るために使うことを考えるべきだ」と。
この言葉には、合成生物学の支持者たちの信念が集約されています。人間の介入を完全に止めることはできない。ならば、その介入をどう倫理的に、科学的に設計するか――。それがこれからの課題なのです。
技術だけではなく、「信頼」が問われている
この議論の核心にあるのは、技術そのものよりも人間への信頼です。合成生物学を推進する人々は、人類が「学習する能力」を信じています。一方、慎重派は、「過去の過ちを繰り返す」人間の傲慢さを恐れています。
「私たちは本当に、自然を再設計し続けるほど賢いのか?」この問いに明確な答えはありません。
合成生物学の問題は、賛成か反対かという単純な構図では語れません。それは、科学の進歩がもたらす希望と危うさ、そして「どこまで人間を自然の一部とみなすか」という思想の問題でもあります。
科学の未来をめぐる社会契約としての議論
IUCNの採択は、技術の全面解禁でも、絶対的な禁止でもありません。むしろ、社会が「科学とどう付き合うか」という新しい契約の始まりを意味しています。
遺伝子改変されたサンゴやカエル、病気に強い樹木が海や森で生きる未来。そのとき、私たちはそれを「自然」と呼べるでしょうか。あるいは、「人工物」として距離を置くでしょうか。
蝶が遺伝子改変された存在だと知ったとき、私たちはそれを同じように美しいと感じるでしょうか。人間の感情や倫理もまた、テクノロジーによって変化を迫られています。
合成生物学は、生命を改造するための道具ではありません。それをどう使うかは、社会の想像力と倫理に委ねられています。いま問われているのは、「技術を使う資格があるか」という、より深い次元の問題です。
科学者のワドルは言います。
「私たちはすでに自然を変えてきた。その力を、ようやく良い方向に使うときが来たのです。」
この「良い方向」とは何か。それを定義するのは、科学者だけではありません。政策、倫理、教育、そして市民社会の議論が不可欠です。
合成生物学はジャズのように、多様で、自由で、即興的な領域です。しかし、即興が美しく響くためには、共有されたルールとリズムが必要です。
自然との関係をどう奏でるのか。そのリズムを合わせる責任は、科学者だけでなく、私たち全員にあります。
すでに登録済みの方は こちら











