【論点#12】ゲノム編集食品は社会に大きなメリットがある✉️29✉️
ゲノム編集の技術は、「安全かどうか」や「リスク」だけで語るものではありません。もちろん、安全性の確認や慎重な評価はとても大切です。しかしそれと同じくらい、この技術が社会にもたらすメリットや将来の可能性にも目を向ける必要があります。
現代社会が直面している食料不足や栄養の偏り、環境破壊、気候変動などの問題に対して、ゲノム編集は具体的で実践的な解決の手助けになる力を持っています。

⭕12の論点の概要は、【やさしいまとめ】、NewsPicksの記事、またはこちらの動画(約15分)をご覧ください。
病・害虫・寄生植物に強い作物:農薬の削減
これまでの農業では、害虫や病気を防ぐために多くの農薬が使われてきました。しかし、農薬は土や水を汚したり、ミツバチなどの生き物に悪い影響を与えたりすることがあります。作物に残った農薬が人の体に入る心配もあります。そのため、「農薬をなるべく使わない農業」が大切になっています。
そこで注目されているのが「ゲノム編集」です。これは作物の遺伝子を少し変えることで、病気、害虫、寄生植物に強くする技術です。昔ながらの品種改良では何年もかかった開発が、この方法なら短い期間でできます。作物が自分の力で病気に負けないようになるため、農薬を減らしても安定した収穫が期待できます。
農薬の量が減れば、土や水、生き物への負担も小さくなります。ミツバチなどの大切な生物を守り、自然の力を生かした持続的な農業がしやすくなります。また、農薬代が減ることで農家の負担も軽くなり、消費者にとっても安全な食べものが増えるという利点があります。
米国のVitisGenプロジェクトでは、ブドウの白カビ病への抵抗性遺伝子を特定し、それをシャルドネなどの高級品種に導入する試みが進行中です。風味や色を変えずに病害を防ぐことが可能となれば、農薬使用量を大幅に削減できる可能性があります。
アフリカの重要穀物ソルガムは、寄生植物「ストライガ(ウィッチウィード)」に悩まされています。このような対策にもゲノム編集は有効です。
つまり、ゲノム編集は作物を強くするだけでなく、環境を守り、農家と消費者のどちらにもメリットをもたらす技術です。これからの時代、持続可能な農業を進めるために欠かせない存在になっていくでしょう。
有機農業+ゲノム編集:有機農業の収量向上
ヨーロッパでは、2030年までに農地の4分の1を有機農業に変えるという大きな目標が進められています。「欧州グリーンディール(European Green Deal)」の一環として、環境や健康にやさしい農業を目指す取り組みですが、有機農業は収穫量が少なく、より広い土地が必要になるという問題があります。結果的に、自然を守るはずの方法が、逆に環境への負担を増やしてしまうおそれもあるのです。
そこで期待されているのが、ゲノム編集による新しい品種づくりです。この技術を使うと、病気や乾燥に強い作物を短期間でつくることができます。たとえば、トウモロコシやイネでは、遺伝子の変化で水の利用効率を高めたり、病気に強くしたりできることがわかっています。こうした技術は、「自然と共に生きる農業」を支える科学の力として注目されています。
しかし、EUの有機農業では、ゲノム編集を使うことが禁止されています。「自然の力を尊重する」という理念のため、人の手による遺伝子操作は認められないのです。そのため、有機農業を広げるうえで、技術を活かせないという矛盾が残っています。
EUは最近、自然に近い方法のゲノム編集作物を「NGT-1」として、従来の品種改良と同じように扱う方向に動き始めました。それでも、有機農業ではまだ使用できず、根本的な問題は解決していません。このため、一部の科学者たちは「有機農業とゲノム編集を組み合わせた新しいカテゴリー」をつくるべきだと提案しています。
こうした議論は、日本にとっても他人事ではありません。気候変動や農家の高齢化が進む中で、干ばつや病気に強い作物をつくることはますます重要になっています。科学の力と現場の知恵をうまく組み合わせることが、これからの食の安全と環境を守る鍵になるのです。
なお、日本の農水省の有機JASでは、ゲノム編集作物については、「2019年12⽉10⽇JAS調査会において、有機JASにおいてゲノム編集技術を原材料等に使⽤できないよう規定を明確にする⽅針が決定。」となっています。
一方で、以下のような動きもあるようです。
栄養価向上:健康指標向上と医療負担軽減
ゲノム編集は、作物の栄養を高めることでも社会に役立つ技術です。今の時代、食べ物の種類は豊富ですが、糖分や脂肪のとりすぎ、ビタミンや鉄分の不足など、栄養のバランスが崩れる人が増えています。その結果、肥満や糖尿病、高血圧、貧血といった病気が増え、これは先進国だけでなく発展途上国でも深刻な問題になっています。
ゲノム編集やGMOを使えば、作物の遺伝子を直接変えて、必要な栄養を増やすことができます。たとえば、ビタミンAを多く含むイモやニンジン、鉄分を強化した米や小麦、野菜などを作ることができます。これによって、子どもや妊婦のように栄養不足になりやすい人たちを守ることができます。
昔ながらの品種改良では、このような作物を作るのに何十年もかかりましたが、ゲノム編集やGMOなら短い期間で実現できます。そのため、栄養不足が起きている地域に早く対応することができます。
さらに、こうした栄養価の高い作物は、学校や病院の食事に使えば健康づくりに役立ちます。発展途上国でも、鉄やビタミンAの不足による病気を防ぐ助けになります。ゲノム編集による栄養強化作物は、健康を守りながら食の質を高める、これからの農業の大切な手段になっていくでしょう。
気候変動対策:農業のレジリエンス
ゲノム編集は、気候変動に強い作物を作るうえで大きな力を発揮します。地球温暖化や異常気象によって、干ばつや洪水、塩害、猛暑や寒波などが増え、作物がうまく育たないことが増えています。これまでの品種では対応しきれず、収穫が不安定になり、農家や食料供給に大きな影響を与えています。
ゲノム編集を使えば、作物がこうした環境ストレスに強くなるように改良できます。たとえば、根の働きを変えて水を効率よく吸えるようにしたり、塩分の多い土地でも育つようにしたりすることが可能です。これにより、干ばつや高温などの影響を受けにくくなり、安定した収穫が期待できます。
また、この技術は環境にもやさしいという利点があります。気候変動に強い作物が増えれば、農薬や化学肥料に頼る必要が減り、環境への負担を軽くできます。さらに、乾燥地帯や沿岸部のように厳しい環境でも農業を続けられるようになり、地域の食料を守ることにもつながります。
カリフォルニア大学バークレーの研究チームは、光合成関連遺伝子の発現をCRISPRで最適化したイネを開発しました。従来のGMOとは異なり、遺伝子そのものではなく調節領域を編集することで、生理的機能を高めています。これにより、水利用効率や高温耐性が向上。将来の食料供給の鍵を握る技術といえるでしょう。
つまり、ゲノム編集は気候変動の時代に欠かせない技術です。異常気象に強く、安定して食料を生産できる作物を作ることで、未来の農業と食の安全を支える重要な役割を果たすと期待されています。
サステイナブルな農業
ゲノム編集は、環境にやさしい「持続可能な農業」を進めるうえで大きな力になります。これまでの農業では、収穫を安定させるために多くの農薬や化学肥料が使われてきましたが、それが土や水を汚し、生き物のすみかにも悪い影響を与えてきました。ゲノム編集を使えば、病気や環境の変化に強い作物を作ることができ、農薬や肥料にあまり頼らずに安定した収穫を得られます。
また、この技術によって、これまで作物を育てにくかった土地でも栽培できるようになります。たとえば、乾燥地や塩分の多い土地でも育つ作物を作れば、使われていなかった土地を活用でき、森林伐採などの環境破壊も防ぐことができます。
さらに、少ない水や肥料で育つ作物を作ることができれば、資源を無駄にせず、環境への負担を減らせます。その結果、土や水の中の生き物を守りながら、自然と共存する農業が実現します。
つまり、ゲノム編集は収穫を増やすだけでなく、環境を守り、資源を大切に使う新しい農業を支える技術なのです。これからの時代、より安全で持続可能な農業を実現するための中心的な役割を果たすことが期待されています。
食品の安全性、食文化の多様性、食品ロス削減
ゲノム編集は、食べものの安全や食文化の多様性を守るうえでも大きな力を発揮します。現代では、アレルギーや食中毒などの問題が増えていますが、ゲノム編集を使えば、アレルギーの原因となる成分を減らしたり、病気に強い作物を作ったりできます。たとえば、小麦やピーナッツのアレルゲンを少なくすれば、これまで食べられなかった人も安心して口にできるようになります。また、病原菌に強い作物を作ることで、食中毒のリスクも下げることができます。
さらに、ゲノム編集は「食の楽しみ」も広げます。味や香り、食感を調整することで、地域の伝統的な味を守りながら、よりおいしくて健康的な食材を作ることができます。たとえば、栄養価が高く甘さを控えた果物や、歯ごたえのよい野菜などがその例です。これにより、健康とおいしさを両立した食生活が可能になります。
また、保存性や病気への強さを高めた作物は、運搬中や保管中の傷みを減らすため、食品ロスを減らすことにもつながります。結果として、安全で栄養のある食品を、より多くの人に安定して届けられるようになります。
切った瞬間に酸化して黒くなる――そんなアボカドの課題にも、CRISPRが挑んでいます。スタートアップGreenVenusは、褐変反応を引き起こす酵素ポリフェノールオキシダーゼをゲノム編集し、変色しないアボカドを開発しました。リンゴやバナナに続くこの改良は、保存性を高めるだけでなく、世界中で問題となっている食品ロス削減にもつながると期待されています。
つまり、ゲノム編集は食の安全を高め、健康的で多様な食文化を未来へつなぐ技術です。私たちの食生活をより豊かで持続可能なものにする、大切な役割を担っているのです。
農業従事者や食品産業のメリット
ゲノム編集の技術は、農家や食品産業にも多くのメリットをもたらします。病気や気候の変化に強い作物を作れるため、安定した収穫ができ、農家のリスクを減らせます。また、農薬や肥料の使用量を減らせることで、コストも下がり、環境にもやさしい農業が実現します。さらに、栄養価の高い作物や美味しさを改良した食品を生み出すことで、消費者の満足度を高め、新しい商品づくりにもつながります。
環境への負担を減らす農業は、企業の社会的責任(CSR)としても評価され、信頼やブランド力を高める効果があります。たとえば、農薬を減らした作物や健康に良い食品を提供することは、持続可能な社会づくりに貢献する取り組みとして注目されます。
米国のスタートアップPairwiseは2024年、世界初となる「種なしブラックベリー」を発表しました。種の硬さを制御する遺伝子をCRISPRで編集し、ブドウのように柔らかく食べられる果実を実現。さらにトゲをなくし、低木化して収穫を容易にするなど、農家にも優しい改良を重ねています。
熱帯地域で重要なタンパク源となるカウピー(ササゲ)は、成長と開花のタイミングがばらつくため、一斉収穫が難しい作物でした。イスラエルのスタートアップBetterSeedsは、CRISPRで花の開花時期を制御する遺伝子を編集し、均一に成熟する品種を開発。機械による大規模収穫が可能になり、農業効率を大幅に改善しています。
また、この技術は地域や国全体の農業にも良い影響を与えます。安定した生産は食料の確保につながり、地域の経済や雇用を支える力にもなります。食品産業や流通業にとっても、安定した原料供給は新しい商品の開発を進める基盤となります。
つまり、ゲノム編集は作物を改良するだけでなく、農家の安定経営、企業の成長、環境保護、そして社会全体の食料安全保障にも役立つ、未来の農業に欠かせない重要な技術なのです。
国際的な視点:食料安全保障と貧困対策
世界では今後、人口が2050年までに約100億人に増えると予測されており、食料の需要も大きく増えます。しかし、気候変動や病害虫の被害によって、今の農業だけでは十分な食料を確保するのが難しくなるおそれがあります。
そこで注目されているのが、ゲノム編集技術です。この技術を使うと、病気や暑さ、乾燥に強い作物を作ることができ、安定した収穫につながります。農薬をあまり使わずに済む作物を育てられるため、環境にもやさしい農業が実現できます。
また、ビタミンやミネラルを多く含む作物を作ることで、発展途上国の栄養不足の問題を改善することもできます。栄養強化作物は、子どもや妊婦の健康を守り、貧困による健康格差を小さくする手助けにもなります。
このように、ゲノム編集は世界の食料不足や栄養問題、環境への負担といった課題を同時に解決できる可能性をもつ技術です。人口が増え続けるこれからの時代に、持続可能な農業と食料の安定を実現するためには、国や国際機関が協力してこの技術を活用していくことが大切です。
まとめ
ゲノム編集の技術には、安全性や倫理、ルールづくりなどの課題がありますが、それらにきちんと向き合えば、社会に大きな利益をもたらすことができます。農業の効率化や環境保護、栄養の改善、食料の安定供給など、さまざまな面で役立つ可能性があるのです。
この技術は、単に作物を改良するための科学技術ではなく、社会全体をより良くするための手段ともいえます。農薬の使用を減らしたり、栄養価を高めたり、気候変動に強い作物を作ったりすることで、環境にも人にもやさしい未来を目指せます。
もちろん、反対の意見もあります。しかし、単に否定するだけでは、このような課題は解決しません。反対意見の中には、明確な根拠がないにもかかわらず、「自分や家族の健康を守るため」といった個人的な動機に基づくものも少なくなく、地球規模での視点や他者への配慮が欠けていることが多いことも問題です。大切なのは、科学的な根拠に基づいて冷静に議論し、どのようにすれば公正かつ安全に活用できるのかを社会全体で考えることです。ゲノム編集は、持続可能な未来を切り開くための重要な技術なのです。
⭕12の論点の概要は、NewsPicksの記事、またはこちらの動画(約15分)をご覧ください。
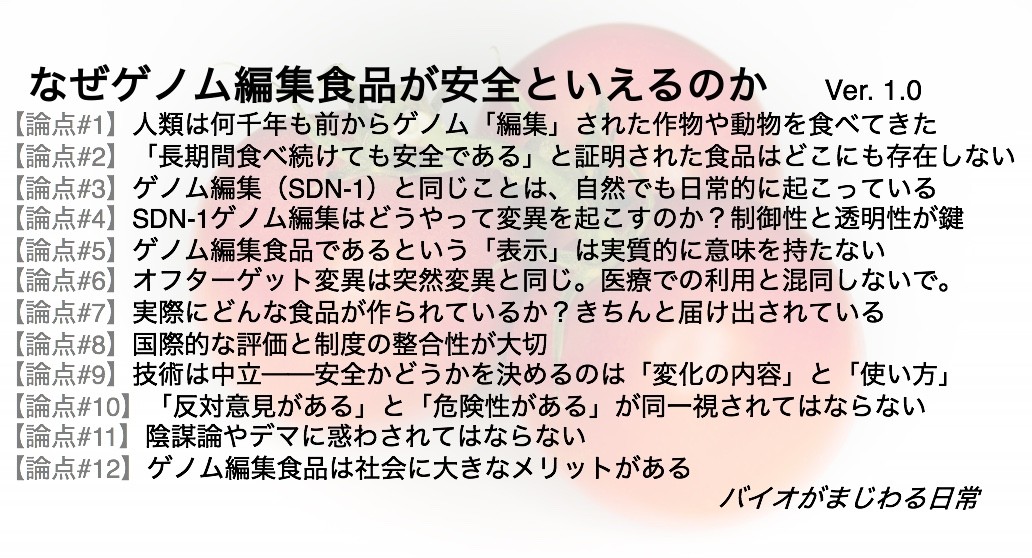
すでに登録済みの方は こちら













