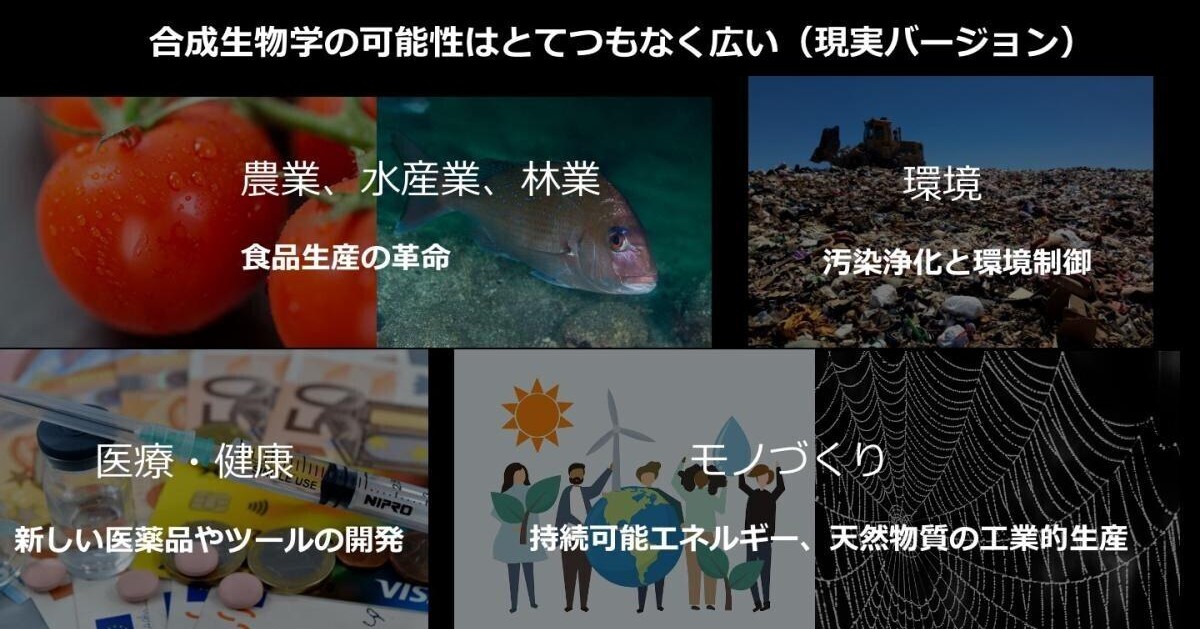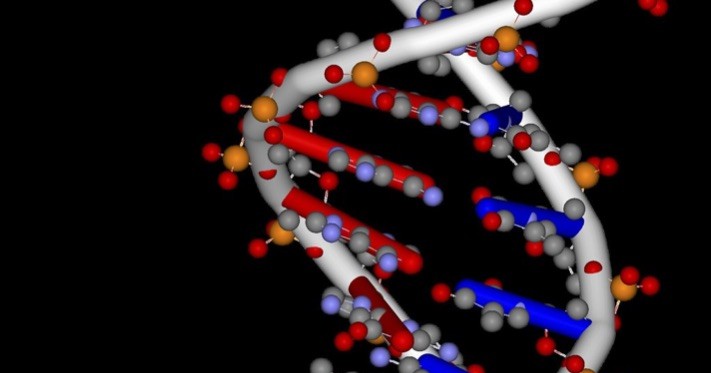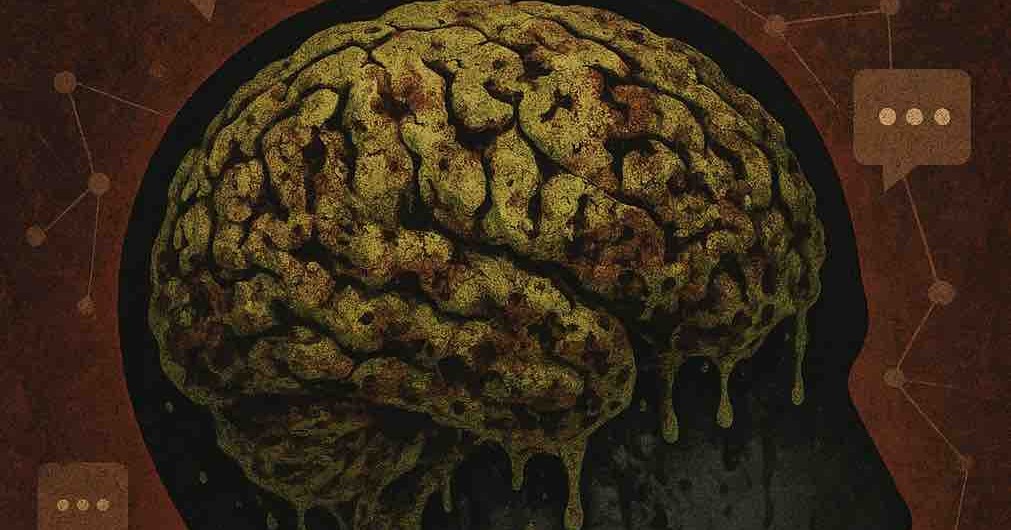小泉八雲が生物を見る目:松江と焼津を訪ねて✉️39✉️
小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は、しばしば「怪談の作家」として語られます。西洋から日本にやってきて、日本の伝承や不可思議な物語を集めた人物、というイメージが一般的です。しかし彼の著作を注意深く読み解くと、八雲が単に「幽霊の物語」を紹介していたのではなく、人間と自然、生命と死、その境界を見つめ続けた思想家であったことが見えてきます。特に彼が示したのは「生物」という存在への強いまなざしでした。
生物とは単なる生き物のことを指すのではありません。八雲の視線においては、人間も動物も植物も、さらには死者の霊すらも「生きているもの」として相互に関係し合っています。そして、その観察眼は驚くほど冷静で科学的であるのです。
しかし、このような奇妙な信仰も、急速に姿を消しつつあります。年を追うごとに、稲荷神社は少しずつ崩れ、二度と再建されないところも増えています。神像も、狐の姿をかたどるものは年々減っています。また、狐憑きとされる人々を、ドイツ語を話す日本の医師のもとで最新の科学的治療を受けさせるケースも、年を追うごとに少なくなっています。この変化の原因は、古い信仰が衰えているからではありません。迷信は宗教よりも長く残るものです。ましてや、西洋からやってきた宣教師たちの布教活動の影響でもありません――彼らの多くは、悪魔の存在を真剣に信じていました。それよりも大きな理由は、教育にあります。迷信に対する最も強力な敵は公立学校であり、そこでは現代科学の教育が宗派や偏見に邪魔されることなく行われています。最も貧しい家庭の子どもたちも、西洋の知識を学ぶことができます。十四歳の少年少女で、ティンダル、ダーウィン、ハクスリー、ハーバート・スペンサーといった偉大な科学者の名前を知らない者はいません。いたずらで神狐の鼻を折る小さな手も、植物の進化や出雲の地質についての文章を書くことができます。新しい研究によって次世代に示された美しい自然界には、幽霊の狐の居場所はありません。迷信を払い、社会を変える力を持つ存在は、まさに子どもたちなのです。
ここで、ティンダルとは、チンダル現象で知られるアイルランド出身の科学者です。小泉八雲の父親もアイルランド出身で、八雲自身はギリシャで生まれ、アイルランドで育ちました。そのため、八雲の英名は、パトリック・ラフカディオ・ハーン(Patrick Lafcadio Hearn)であり、パトリックというアイルランド風の名前を持つのです。
八雲は動物に深い関心を抱いていました。特に猫を愛したことは有名で、彼の著作には猫にまつわる逸話が数多く登場します。
私は猫が大好きである。さまざまな気候風土とさまざまな時節に私がこの地球の両側で飼ってきたいろいろな猫について、一冊分厚い書物が書けるのではないか、と思っているほどだ。
また、昆虫へのまなざしも特筆すべき点です。晩年、しばしば訪れた静岡県の焼津では、トンボなどの採集に興じていた姿が見られたそうです。八雲は『昆虫記』で知られるジャン=アンリ・ファーブルに強い影響を受け、自らも昆虫の生態に深い関心を寄せました。エッセイ「虫の音楽家たち」では、日本の異なる時代に詠まれた秋の虫の鳴き声の記述を紹介し、昆虫の音色が人間の感情にどのような影響を与えるかを論じています。
松江の街を歩く
小泉八雲が日本に来て最初に住むことになった島根県松江市には今も多くの稲荷社があります。稲荷信仰は農耕と商売の繁栄を祈る庶民の信仰でありながら、狐の霊や境界の神として不思議な伝承を生み出しました。ハーンはそうした民間信仰に強い興味を抱き、西洋的な合理主義では割り切れない日本人の精神の奥行きを見出しました。
宍道湖の夕暮れを眺めながら、私は彼が見たであろう景色を想像します。湖面に映る陽の光がゆるやかに色を変え、やがて闇に包まれていくその時間に、ハーンはどこか懐かしさを感じたのかもしれません。彼の筆は、日本の風景の美しさだけでなく、その背後にある信仰や物語の記憶をもすくい取ろうとしたのです。
現在の松江を歩くと、城下町の落ち着いた雰囲気とともに、八雲ゆかりの地を示す案内板が点在しています。
また、彼が松江で最初に住んだ旧居は、こぢんまりとした日本家屋で、ハーンがどのような思いで異国の土地に短い期間でしたが身を置いたのかを想像できます。そこには、近代化の波に揺れる日本の姿と、それに魅せられつつも郷愁を抱えた一人の作家の姿が重なります。
八雲の文学の背後には、常にセツの存在があったということです。彼が出会った日本文化は、単に風景や制度ではなく、人々の記憶と物語の世界でした。そして、その扉を開いたのは、庶民の生活を知るセツの語りと感性でした。稲荷の杜に立ち、狐の像を見上げていると、この土地の女性の語りがいかに文化をつないできたかを思わず考えさせられます。




焼津の町
小泉八雲は静岡県焼津の海での海水浴が気に入り、夏が来ると、焼津で過ごしていました。
焼津の町並みは港町らしい素朴さと活気が混ざり合っています。漁港では朝早くから漁師たちの声が響き、魚市場では新鮮な魚介類が並びます。魚屋に滞在した八雲がここで目にした風景も、きっと人々の暮らしと海の営みが密接に結びついたものだったでしょう。彼は港の賑わいを単なる景色としてではなく、人々の生活と物語を映す鏡として見つめたのだと思われます。
町の路地を歩くと、漁師の家々や小さな商店が連なり、どこか懐かしい日本の庶民的な日常が感じられます。ヤマトタケルが東征の途上、賊に襲われた際に草薙剣で葦を薙ぎ払い、火を放って難を逃れたという伝承が残る焼津は、島根と並んで神話の地としても知られています。



港町の一角に立ち、波の音に耳を澄ませていると、八雲がそこに立ち、同じ風景を眺めながら筆を走らせていた光景が目に浮かぶようです。松江の稲荷社で見た神秘的な空気と、焼津の海で感じた生き生きとした人々の営みは、彼の作品の中で絶妙に交錯し、日本の文化と自然、そして人々の物語が融合した独特の世界を形作ったのだと感じます。
すでに登録済みの方は こちら