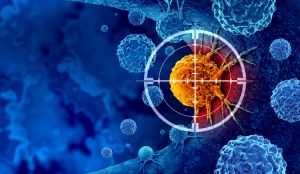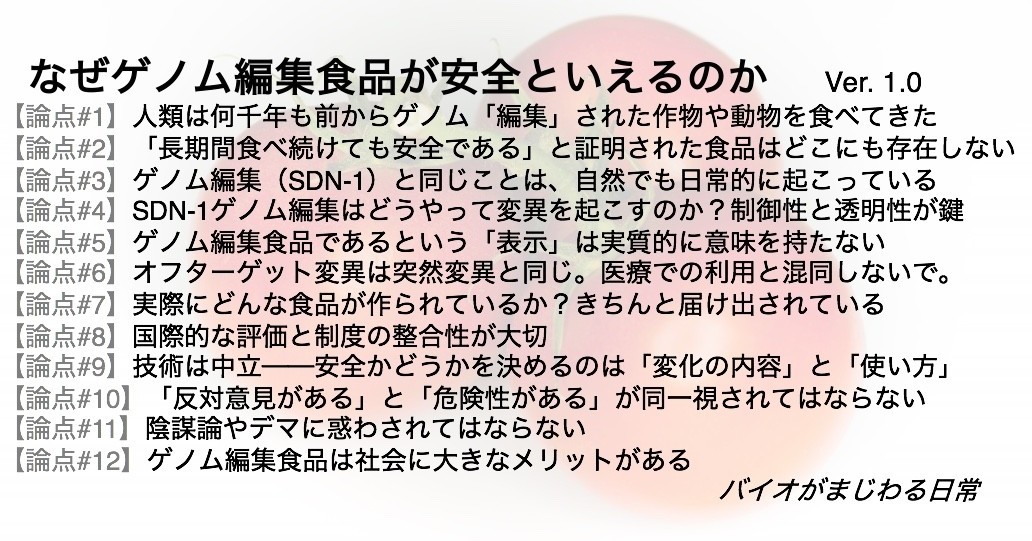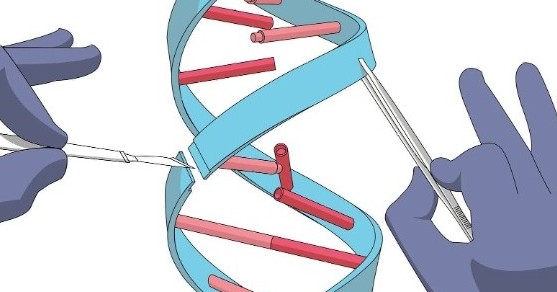ひとつの発見が世界を変える――坂口志文と免疫学の系譜✉️21✉️
みなさんは、ノーベル賞と聞くと、「その人の一生の功績に対して贈られるもの」というイメージをお持ちではないでしょうか。メディアのノーベル賞紹介記事、とくに「予想」に関する記事を見ていると、記者の方々がそう考えているのではないかと感じることが、しばしばあります。
しかし、そうではありません。以前ハーバード大学で、スウェーデンから来たノーベル生理学・医学賞の選考委員の方と食事をしたとき、その方がこう言ったのです。
「ノーベル賞は研究者としての生涯の功績に対してではなく、一つの発見に対して与えられる賞である」
日本の文化勲章などは、その人が長年にわたって学問を発展させ、多くの論文を発表し、学会、教育や社会にも貢献してきたことが総合的に評価されます。でもノーベル賞は違います。世界の見方を変えるような「ひとつの発見」「ひとつの研究」こそが評価されるのです。私は毎年ノーベル賞の発表があるたびに、その「ひとつの発見」とはどの研究だったのか?どの論文だったのか、と考えます。
がん・自己免疫の治療を変えた発見
2025年、その「ひとつの発見」で世界から注目されたのが、日本の坂口志文(さかぐちしもん)さんです。坂口さんは、がんや自己免疫疾患の治療法に革命をもたらすとされる「制御性T細胞(Treg)」を発見しました。その研究の軌跡は、こちらのWedgeの記事やJT生命誌研究館の記事が興味深いです

こちらのNewspicksに私が書いた新しい記事は、今回の文章とも重複しますが、リンクや親しみやすい内容を充実させてあります。
免疫は、本来ウイルスやがん細胞など“敵”を攻撃しますが、時には誤って自分自身を攻撃してしまい、関節リウマチや1型糖尿病などの自己免疫疾患を引き起こします。制御性T細胞は、この暴走を防ぐブレーキ役を果たす特別な免疫細胞です。
この発見がすごいのは、免疫を単に「活性化」するだけではなく、「適切に抑える」という新しい考え方を医療に導入したことです。すでに臨床試験が進んでいて、自己免疫疾患や臓器移植の拒絶反応の治療など、幅広い応用が期待されています。
共同受賞者は、メアリー・E・ブランコウ氏、フレッド・ラムズデル氏。科学についての詳細は今後さまざまなソースが発表されるでしょうから、そちらに譲りたいと思います。
先人の夢を引き継ぐ
坂口さんの道のりは決して平坦ではありませんでした。その背景には、日本の免疫学を支えた先人たちの挑戦があります。
たとえば1970年代、免疫学者の多田富雄(ただとみお)さんは、「免疫を抑える特別なT細胞(サプレッサーT細胞)が存在する」という大胆な仮説を提唱しました。当時は証明する技術がなく、多くの研究者に否定されました。
それから約20年後、坂口さんは制御性T細胞を発見します。それは、まさに多田さんが夢見た“免疫のブレーキ役”だったのです。多田さんの未完の仮説は、坂口さんの実験によって現実のものとなりました。
坂口さんの研究人生の原点には、愛知県がんセンターの病理学者だった西塚泰章(にしづかやすあき)さんとの出会いがありました。さらに西塚さんの兄弟・西塚泰美(やすよし)さんは、細胞内でのシグナル伝達に関わるプロテインキナーゼCという酵素を発見し、存命中には、いつもノーベル賞の候補者になっていました。また、西塚泰美さんは、がん治療に革命を起こした免疫療法で2018年にノーベル賞を受賞した本庶佑さんの師匠でもあります。
日本の免疫学の強み
坂口さんの発見の背後には、日本ならではの学問の土壌があります。免疫学は国際的な競争が激しい分野ですが、日本には長年、層の厚い研究者コミュニティがあり、互いに切磋琢磨してきました。
地味なように見える動物実験の積み重ねや、顕微鏡による観察を大切にする姿勢です。そこには派手さはありませんが、生命の複雑な仕組みを理解するうえで不可欠な要素でした。
坂口さんは、制御性T細胞の知識を応用して新しい免疫治療を開発するために、バイオベンチャー企業「レグセル」を立ち上げました。基礎研究だけでなく、その成果を社会に還元しようとする姿勢も特徴的です。
今後、免疫学はAI解析やシングルセル技術(細胞一つひとつを解析する技術)の発展によって、さらに精密な治療が可能になると考えられます。しかし、どれほど技術が進んでも、現場での観察や仮説を粘り強く確かめる姿勢は変わらないでしょう。
学問は人をつなぎ、時を超える
坂口さんの研究は、一人の天才のひらめきではなく、先人たちが残した問いと夢を引き継ぎ、長年の努力で証拠を積み上げてきた結果です。その歩みは、学問の進歩がどれほど時間のかかる営みであるかを教えてくれます。
学問は過去と現在をつなぎ、未来を形づくります。坂口さんの物語は、日本の知の系譜と、その先に広がる医学の新しい地平を示しています。そして、これからも多くの若い研究者たちがこの道を歩み、免疫の仕組みを解き明かし、よりよい治療法を作り出していくでしょう。
すでに登録済みの方は こちら